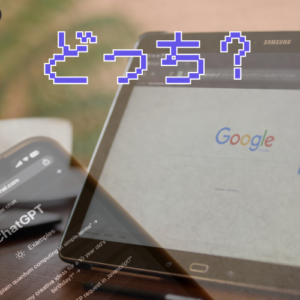マズローの欲求5段階説は、多くのビジネスや自己啓発の場面で使われてきました。
しかし、時代の変化とともに、「5段階では説明しきれない」と感じる人も増えてきています。
特に、モチベーション3.0やデザイン思考、持続可能なハードワークなど、新しい概念が登場し、組織をどう動かすべきかの議論が進んでいます。
そんな中、マズローが晩年に提唱した「自己超越」という概念が再び注目を集めています。
彼は、人間の欲求は5段階で終わるものではなく、さらに高次の「自己超越」があると考えました。
これこそが、個人の生きがい、ひいては組織のあり方に大きく関わってくるのではないでしょうか?
「働きがい」ではなく「生きがい」を重視する
組織の構成員は、単なる労働力ではなく、一人ひとりが自分の人生を生きる個人です。
「働きがい」が重要であることは言うまでもありませんが、それを超えて「生きがい」にまで目を向けることが、組織の持続的成長につながります。
もし「働きがい」だけを重視しすぎると、燃え尽き症候群(バーンアウト)になる可能性があります。
では、どうすればよいのか?
企業が「何のために存在しているのか」という本質的な問いに向き合うことが重要です。
多くの企業が掲げる経営理念は、最終的には社会貢献に帰結します。この「社会のために」という視点こそが、マズローの言う「自己超越」と深くつながるのです。
自己超越を実践する企業の考え方
興味深いことに、すでに「自己超越」を体現している企業も存在します。
例えば、利益追求だけでなく、社会的な価値を生み出すことを重視し、従業員が会社の理念に共感しながら働いている企業があります。
こうした企業では、組織の結束力や従業員のモチベーションが高まり、結果として持続可能な成長につながっています。

組織運営の新たな視点:「キャンプファイヤー型」の組織
従業員を「駒」として扱うのではなく、一人ひとりの心を尊重することが大切です。
従来の「飴と鞭」だけでは、人の心を本当に動かすことはできません。
では、どんな組織を目指すべきでしょうか?
一つのヒントとして、「上下関係ではなく、同士としての関係を築く」ことが挙げられます。
例えば、キャンプファイヤーを囲むように、リーダーとメンバーが対等に議論し、共に未来を考える組織です。
「自己超越」を取り入れるためにできること
「言うは易く行うは難し」とはよく言われますが、実際に自己超越の考え方を組織に取り入れるには、次のステップが重要です。
- 小さな取り組みから始める:すべてを一気に変えようとせず、できることから少しずつ実行する。
- 従業員を巻き込む:トップダウンではなく、従業員とともに考え、共に動く。
- 心理的安全性を確保する:自由に意見が言える環境を作ることで、個々の成長を促す。
- 経営者も相談相手を持つ:リーダー自身も孤立せず、信頼できる相談相手を持つことが大切。
まとめ
マズローの6段階説における「自己超越」は、単なる理論ではなく、現代の組織経営において非常に重要な視点です。
「働きがい」だけではなく「生きがい」を考え、個人と組織の成長を両立させることで、持続可能な企業文化が生まれます。
そして、経営者自身も相談相手を持つことが重要です。
リーダーが孤立せず、信頼できるパートナーと共に進むことで、より良い組織づくりが可能になります。
この記事を書いた人
 山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。