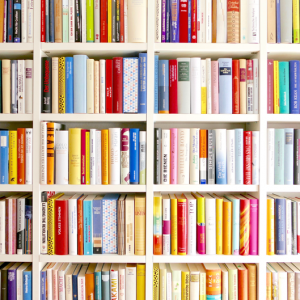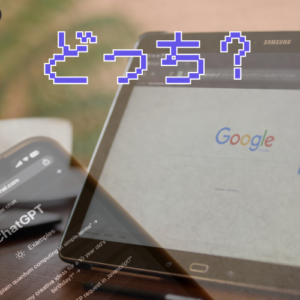私たちは日々、何かを信じて生きています。
宗教やカルトに心酔する人々がいるのは、「信じること」が人間にとって自然な営みだからです。
しかし、それは一部の宗教やカルトが、時に人々を操り、過激な行動に駆り立てる危険もはらんでいます。
ここで考えてみたいのは、こうした宗教やカルトのマーケティング手法が、なぜこれほどまでに人を動かすのか、そしてその仕組みをビジネスに応用できないかという点です。
目次
実はビジネスでも使われている“カルト的手法”
「カルト的マーケティング」などというと恐ろしい印象を受けるかもしれませんが、実際には現代のビジネスやマーケティングにおいても、そのエッセンスはすでに使われています。
たとえば、強い理念に共感させ、共通の敵を設定して連帯感を作り出す手法。
これらは宗教やカルトが用いてきた人の心を動かす仕組みそのものです。
ブランド戦略やコミュニティビジネス、サブカルチャーの形成などでも多用されています。
強い理念と共通敵が人を突き動かす
カルト的マーケティングの基本構造は、非常にシンプルです。
-
理念の設定:人々が心から共感できる明確な理念を掲げる
-
理想の提示:現状からの脱却を促し、理想の未来像を見せる
-
共通敵の設定:理念を実現するために「乗り越えるべき敵」を明確化する
このとき、理念が強ければ強いほど、敵が明確であればあるほど、人々は熱狂し、行動を共にするようになります。
これは宗教に限らず、企業のブランディングでも同じことが言えます。
例えば、「サステナブルな未来をつくる」という理念を掲げる企業は、「大量生産・大量消費」「使い捨て文化」「化石燃料依存」といった共通の敵を設定しやすいのです。
ビジネスの視点から例を考えてみる
オーガニックとフェアトレードの戦略
「オーガニック」「フェアトレード」を掲げるブランドは、強い倫理的理念と社会的責任感を訴え、消費者に“良いことをしている自分”という満足感を提供します。
そして対極に位置づけられるのが、ファストファッションや児童労働問題といった共通敵です。
地球環境とエネルギー問題
「地球環境を守る」という理念を掲げ、化石燃料の大量消費を敵とし、再生可能エネルギーや脱炭素社会を目指す動きもまた、宗教的ともいえるほどの信念と団結を見せています。

カルトとビジネスの境界線
理想、共通敵、差異の強調、仲間意識の醸成、そして階層化による競争。
これはまさに宗教やカルトの構造そのものであり、マーケティングの強力なツールにもなり得ます。
しかし、ここで問題となるのが「倫理観」です。
理念を掲げるリーダーが教祖化し、上位階層への“献身”が求められはじめたとき、それはマーケティングではなく、支配構造へと変質していきます。
お金も時間も「信仰」の名のもとに差し出され、個人の自由が奪われていく。
この状態では、もはやビジネスとしての健全性は保たれているとはいえなくなるのではないでしょうか。
理念と共通敵を扱うマーケティングには高い倫理観が必要
宗教やカルトが人々の心を掴み続けているのは、人間の本質に深く刺さる仕組みがあるからです。
そして、それはビジネスにおいても、顧客や従業員を一つの方向へ熱狂的に向かわせる力となり得ます。
しかしそれは、使い方を誤れば組織の破綻や社会的混乱を引き起こす劇薬でもあります。
だからこそ、理念を掲げ、共通敵を設定するマーケティングには、深い倫理観と公共的な視点が欠かせません。
マーケティングは「自己超越」の手段になり得る
最終的には、自分や企業が社会全体のために貢献しているかを常に問うことが重要です。
これは心理学者マズローが提唱した「自己超越」にも通じる考え方であり、人間が最終的に求めるのは「誰かのために生きている」という実感です。
単なるテクニックに終始せず、理念を社会善に結びつけること。
それが、宗教やカルトに学びながらも、ビジネスとしてまっとうな道を歩む唯一の方法なのだと思います。
この記事を書いた人
 山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。